 外来種
外来種 冬に綺麗な花を咲かせる「スイセン」は、ホントはよその国の花だった!!
冬に咲く美しいスイセン(水仙)は、昔々地中海沿岸地域から中国を経てわが国に渡来した外来種です。わが国の固有種と思われるほど、冬から春になくてはならない花です。愛される花なんですが、実は、有毒で毎年のように誤食がニュースなったりします。
 外来種
外来種  外来種
外来種  外来種
外来種  採取
採取  知識のお花畑
知識のお花畑  在来種
在来種 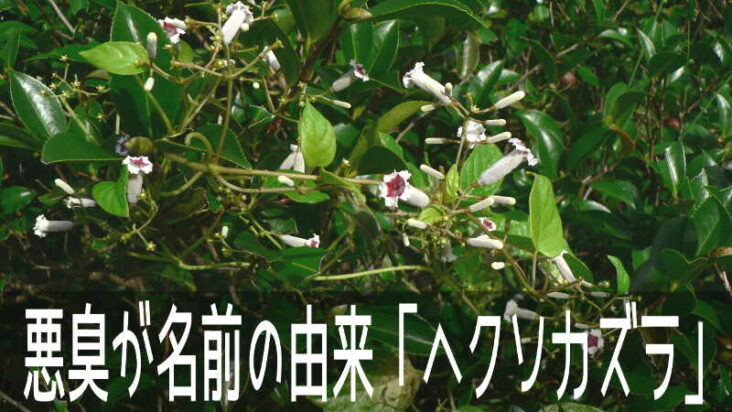 在来種
在来種  外来種
外来種  在来種
在来種  在来種
在来種